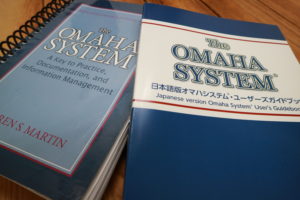兵庫県北部に位置する豊岡町で、訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護(看多機)を運営する、一般社団法人 ソーシャルデザインリガレッセ。
「看護はもっと日常の暮らしの側にあるべきもの」という思いの元、看護師の大槻恭子さんが多くの方のサポートを受けて立ち上げた場所です。
ラテン語の「リガーレ(繋がる、紡ぐ)」と「エッセ(存在)」を組み合わせた造語であるリガレッセ。「存在を繋ぐ」という名前には、どのような意味が込められているのでしょうか。また、過疎化が進む町で、地域における看護師の役割とはどういったものなのでしょうか。大槻さんにお話を聞きました。

大槻恭子。一般社団法人 ソーシャルデザインリガレッセ代表。京都府出身。奈良の病院で看護師として勤務したのち、子供の病気をきっかけに養父市に移住。公立病院で訪問看護の経験を積み、2015年にリガレッセを立ち上げる。
患者さんの痛みに向き合えない苦しさを感じていた

「病院で働いていた頃は、病院のスピーディーさと、患者さんにしっかり向き合いたいという気持ちとのミスマッチをずっと感じていました。時間をかけて患者さん本人やご家族の痛みや苦しみに寄り添いたいと思っているのに、お薬を投与するしかできない状況にもどかしさがありましたね」
リガレッセ代表の大槻恭子さんは、看護学校を卒業後、病院の看護師としてキャリアをスタートしました。看護学校で在宅看護の実習を受けたときから「在宅の世界にこそ私が求める看護の形がある」と感じていたという大槻さん。訪問看護への憧れはあったものの、「新人看護師が在宅(看護)なんて」という風潮が強かったため、まずは経験を積もうと選んだ職場でした。
「看護を学んできたから、患者さんの痛みを取り除く方法は痛み止めだけじゃないと知っているんです。精神的な苦しさや家族とのわだかまりが痛みとなって出てくることもあると学んでるのに、そこにしっかり向き合えないのは苦しかったです」
その後結婚・出産を経て、兵庫県の公立病院で、願っていた在宅看護の仕事に就くことになります。しかしそこでぶつかったのは「在宅だからといって望む看護ができるわけじゃない」という現実でした。
「公立病院は公務になるので、暮らしのケアにどうしても制限がかかりやすいのですよね。ある日、利用者さんに『スーパーへ買い物に行きたい』と言われたので、屋外歩行のリハビリがてら行くことにしたら、後から『スーパーに行くなんてダメ』とすごく怒られてしまって。後日利用者さんにその顛末を伝えたら、返ってきた言葉は『じゃあリハビリする意味ないわ』でした。これはグサッときましたね」

本来リハビリのモチベーションはやりたいことがあってこそ生まれるものなのに、その目的を自分が削いでしまうというジレンマ。この経験は、大槻さんの「自分の訪問看護ステーションを持ちたい」という気持ちを大きく後押ししました。
“治療の場”ではなく“暮らしの場”として
そこからリガレッセを創設するまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。家族のとある問題を機に縁もゆかりもない兵庫県北部に移住し、よそ者への強い風当たりの中、大槻さんは訪問看護ステーションを立ち上げるべく準備を推し進めました。
「私は地元の人間じゃないので、地域の方の信頼を得るまでは本当に大変でした。そんな状況の中でも這いつくばってやってきたのは、看護師がきちんとケアに向き合って運営するステーションを作りたいという思いがあったからです」
その思いが実を結んだのは2015年。大槻さんはリガレッセでの最初の事業である訪問看護ステーションを立ち上げました。アパートの小さな一室でのスタートでした。


訪問看護ステーションに続き、2017年には看護小規模多機能型居宅介護支援事業所を開所。病院や公立病院ではできないケアを提供するために、リガレッセでは一貫して「一人ひとりの人生にきちんと向き合うこと」を重視しています。
リガレッセの大前提は、“治療の場”ではなく“暮らしの場”であるということ。「目的は治療ではなくその人らしく生きることなので、利用者の“生きる力”を信じるアプローチをしています」と語る大槻さんが、それを体現するために特に大事にしているのが、食事を口から食べることです。
「病院でごはんを食べられなかった方がもう一度食べられるようになり、2年、3年元気で過ごしているってよくあることなんです。入院によるネガティブな心理状態から食べられなくなるケースもあるので、『本当に食べられないのか?』は常に疑いたいんです」

口から食べるためには、毎日丁寧に嚥下機能を上げるアプローチをすることが必要です。ときには豪華なお弁当を用意して中庭でのランチに誘うなど、気分を前向きにするような工夫もするそう。
「時間もかかりますし、個々人の特性を捉えるための丁寧な関わりも必要になる。でも『どうやったらできるか』を考えながら、利用者さんの生きる力を信じて関わることで、たくさんのケアが生まれるんです」
「スーパーに行きたい」という利用者の希望を断らざるを得なかった苦い経験が、リガレッセの運営方針に活きています。「好きなものを食べたい」「外に出て新鮮な空気を吸いたい」といった利用者の希望をどのように叶えていくか。看護師が「看護とは何か」を突き詰めて考えていくことが看護のあり方を広げていくことに繋がると、大槻さんは信じています。
家族や地域に看護師が介入するということ

一人ひとりに向き合うケアに加え、大槻さんがもう一つ大切にしているのは「地域の中の看護のあり方」です。それぞれの家庭の苦しみに看護師が第三者として介入していくことで、地域から苦しみの総量が少なくなっていく——それが大槻さんの考え方です。その背景には、自身が家庭内での問題を抱えた経験がありました。
「私は離婚も経験しているんです。当時は家庭内の不調から、出口の見えない日々が続きました。10年くらい、改善できるようにといろんなことをやってきたんですよね。看護師だからどこかその状況を客観的に見てしまう自分もいて、当事者だけで話しても絶対に解決しないとわかりきっていたのに」
家族で問題を抱えたとき、それを自分たちだけで解決するのはとても難しいことだと、大槻さんは身をもって気づいたといいます。第三者として客観的な立場で家族に関わる役割を看護師が担えるのではないか。それが大槻さんの仮説です。
「訪問看護でいろんなご家族を見てきた中で言えるのは、どの家にも必ずなにか問題はあるということ。特に病気や介護をきっかけにその問題が顕在化することは多いです。そんなとき、病院だけでなく日常に近いところで看護師が携わることで、地域の苦しみを軽減できる気がするんです」

家族間や地域のコミュニケーションに看護師が介入するために、大槻さんは「物語としての命に向き合う」ことを大切にしています。それは、生まれてからこれまで生きてきたその人の軌跡を尊重するということ。目の前の命を「物語」として捉えることで、より豊かに、わだかまりなく人生の終わりに立ち会える。これまでの経験から、大槻さんはそう感じるようになったといいます。
「目の前の方が死を目前に苦しそうにしていたりすると、家族や周りの人は“今”に注目して、『苦しそう、どうしよう』と焦ってしまいます。病院での治療の場合、死は敗北を意味することも多いので、最期まで点滴をしっかり入れたり血圧の値を注視したりしますよね。私たちの場合は、看護師が少し俯瞰した視点で『どんなお父さんだったんですか?』『どんなことを大切にされている方だったんですか?』とファシリテートしていく。
そうすると、その場の会話が変わります。『この人、普段は怖いけどかわいいところもあるんよ』みたいな話になる。今の死を目前にした苦しさではなく、その人が歩んできた人生を見つめることで家族もふっと楽になって、時間がないことに対する焦りが小さくなるんだと思います」
大槻さんは「死」ではなく「生を閉じる」という言葉を使います。最後まできちんと生きて、暮らしの中で生を閉じていく。姿形はなくても、みんなの中で存在として生き続ける。そういった命の捉え方をすることは利用者の家族のケアにも繋がり、ひいては地域全体の豊かさにも繋がっていくと大槻さんは考えています。
家族の定義を拡張すれば、在宅ケアの可能性も広がっていく

リガレッセのある兵庫県豊岡市日高町は、他の多くの地域と同じく高齢化が進む過疎地域です。独居の高齢者も多く、訪問看護や看多機を必要とする人の数は今後どんどん増えていくことが見込まれます。
多くの人にケアが行き届くようにすることと、一人ひとりの命と丁寧に向き合うこと。その二つを両立するためには、まだまだ多くの課題があるといいます。
「課題はいろいろありますが、在宅看護ができることを広げていくためには、まず家族の定義を広げていく必要があると感じています。たとえば、最期を病院で迎えるのか家で過ごすのかの意思決定は、本人ができない場合家族の代理決定に委ねられることになりますが、独居の方や家族とうまくいっていない方には代理決定ができる方がいないんです」
そのほかにも吸引の処置など、血縁関係のある家族にしかできないものもあります。家族がいない人はサービス関係者に頼らざるを得ず、「吸引できる人がいないから、本人は在宅を望んでいても家で過ごせない」というケースもあるそうです。
「公民館やコミュニティセンターのメンバー同士で代理決定ができるような組織があるとか、新しい家族の概念みたいなものがあればいいのになと思います。血縁関係がなくても『私たちって家族だよね』が叶うと、在宅ケアの可能性は広がっていくと思います」
今後日本の多くの地域は、日高町と同じような状況に置かれるはずです。そのとき、最後まで「物語としての命」を尊重してくれる場所があれば。血縁に限らず「家族」と呼べる人たちとの関わりの中で生を閉じられたら。地域は今よりもずっと豊かな場所になっていくのかもしれません。