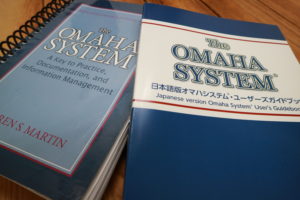「訪問看護師」と聞いて、病院で経験を積んだ看護師が選ぶキャリアのひとつ。そうイメージする方もいるのではないでしょうか。
「病院で働いた経験のない新卒の自分が、いきなり訪問看護の現場でやっていけるのかな」。看護学校卒業後すぐに訪問看護の道に進みたくても、不安だったり自信を持てなかったりして、まずは病院で働く選択をする人は少なくありません。
しかし、新卒で訪問看護師を志願する人もいます。そして、彼らを受け入れる訪問看護ステーションもあります。今回お話を伺うのは、ウィル訪問看護ステーション江戸川に、2018年4月に入所した看護師の関口優樹さん。
看護師の母に育てられ、中学生のとき「心のケアもできる看護師になりたい」と夢を持って、看護学部のある大学に進学します。「卒業後は病院で働くと思っていました」と語る関口さんが、新卒×訪問看護というキャリアを選ぶまでと、選んでからのことを聞きました。
障害や病気と共に、自分らしく生きる人との出会い
関口さんの進路決定に大きな影響を与えたのは、大学時代に注力していたふたつの活動だといいます。
ひとつは、NPO法人soarで2〜3年次にインターン生として働いたこと。障害や難病を抱えた人をはじめ、社会的マイノリティの人々を取り上げ、一人ひとりの持つ可能性を伝えるWebメディア「soar」の運営に携わりました。

「soarで学んだことは、多様な人と向き合う姿勢です。障害や病気は決してネガティブなことばかりではなく、強みとしてその人らしく生きている人もいること。障害はその人個人にあるものでなく、社会や環境が創り出しているものであること。綺麗事ばかりではなく生きづらい世の中だけど、それでも誰もが可能性をもって生きていること。soarで学んだこれらのことは看護師になった今も大切にしています。」
もうひとつは、自己分析から導き出された「自分が本当にしたいこと」をベースに、イベントやプロジェクトを実施する学生団体での経験です。自己分析の結果、自分がしたいのは、一人ひとりがその人らしくいられるような「場作りや地域作り」だと気づいた関口さん。

活動を通じて、放課後等デイサービスや看護小規模多機能施設など、地域に根ざした組織で働く人たちに話を聞きにいったり、企画を主催して多様性や地域について知る・広める活動をしていました。
「障害や病気を持った人たちが、慣れ親しんだ地域で暮らす姿は、とてもイキイキとして見えました。そんな経験も訪問看護に興味を持つきっかけになりましたね」
ひとりで現場に行くけど、ひとりじゃない安心感
3年生の秋に、新卒でも訪問看護師になれると知り、4年生になる前から訪問看護ステーションに絞り込んだ就職活動を始めます。その中でも、新卒であり医療的な観点も学んでいきたいため、介護やリハビリよりも、医療的ケアの利用者の割合が高い訪問看護ステーションに定めました。
訪問に同行させてもらったり、事業所の雰囲気を見せてもらったり、足を運んだステーションは6〜7カ所に及びました。そのなかで、ウィル訪問看護ステーションが掲げる「全ての人へ家に帰る選択肢を」といった理念や、それを実践しながら働く先輩たちの姿に共感を抱き、ウィル訪問看護ステーションを志望します。
特に「“選択肢”という部分に惹かれた」と関口さんは言います。あくまで看護は選択肢を提供するのであって、選択は利用者自身がする。利用者主体の看護が展開していけると感じたそうです。
入所から2〜3カ月の時期を、関口さんは「何がわからないのかがわからない状態だった」と話します。その期間はすべて先輩看護師との同行で、先輩に見守られながら患者さんのケアをサポート。訪問1件ごとに振り返りの時間を設け、訪問中疑問に感じたことを先輩に聞き、自分の糧にしていきました。

4カ月目からは同行訪問が減り、ひとりでの訪問看護も始まります。初の単独訪問のことは「今でもはっきり覚えています。ずっと先輩の訪問に同行していた患者さんでしたが、いざひとりで訪問するとなると緊張しすぎて、チャイムを鳴らす前にフーッと深呼吸しました」と振り返ります。緊張の理由は、もし患者さんが部屋で倒れていたら……という想像からくるもの。
「単独で訪問するようになって1〜2カ月は、訪問が1件終わる度に先輩に報告の電話をしていました。訪問看護は基本的に、ひとりで訪問するのですが、実際はひとりで看護を実践している感覚はその不安は大きくありません。電話や事業所専用のチャット等ですぐに先輩や先生と連絡がとれたり、患者さんやご家族、他職種の皆さんと共同して実施していくので。不安もありますが、周りの方々に支えられながら訪問看護を実践することができています 」
死を受け入れて、次に活かす勇気
昔から人と話すのが好きで、訪問先で患者さんのこれまでの人生や大事にしている考え方など、一人ひとりの思想や価値観にふれて、それらを治療計画に落とし込む。自分が望んでいた仕事ができる環境で、やりがいを感じていた関口さんでしたが、心が折れそうになる時期がありました。
3カ月ほど、週に一度の頻度で訪問していた高齢患者さんの死ーー。ガンにかかっていて、あるときから緊急連絡が度々来るようにもなっていました。関口さんが最後に訪問して約1週間経ったころ、高齢者住宅のスタッフを通じて、患者さんの訃報が届いたときはショックだったといいます。
「責任のようなものを感じてつらくなり、その日は先輩に話を聞いてもらいながら、たくさん泣きました。それからしばらくは、ひとりで訪問するのが怖かった、というのが正直な気持ちです。でも、死は誰にでもやってくるもの。受け入れざるを得ないし、次に活かすしかないと考え方を変えました」
一人ひとりにとって最良の看護を考えられる人になりたい
患者さんから教わることは多い、と関口さんは話します。患者さんひとりにつき◯分、とケアの時間をしっかり確保でき、その人がその人らしく過ごせる家でケアできる訪問看護だからこそ、より深く密なコミュニケーションがしやすいというのです。

「患者さんにとっての“ホーム”に出向くと、一人ひとりを多面的に見ることができるんです。たとえば、ある男性患者さんは、孫を可愛がるおじいちゃんで、商店を開いている経営者で、釣りという趣味を持つ人でもある……というふうに、いろいろな顔を持っています。
患者さんがいろいろな“顔”を持っている人だと意識する瞬間に出会うことがあります。在宅医療はその人を取り囲む環境や人々、情報、あらゆるものをひっくるめて見ることができるぶん、その人にとって何が最良の看護なのか考えやすい。それが訪問看護の魅力だと感じています」
4月には入所2年目を迎える関口さん。家族や周囲の人、地域資源などを積極的に巻き込みながら、その人が地域でより良く過ごす方法を広い視野で考えられるようになりたい、と新たな目標を語ってくれました。